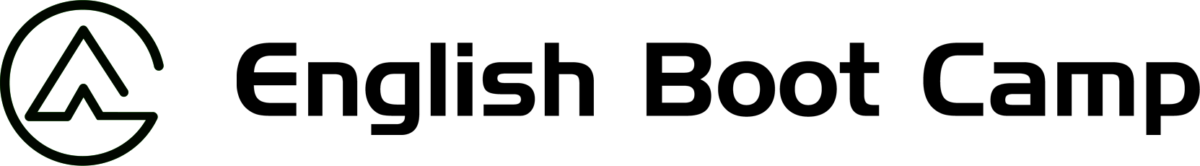皆さんこんにちは。イングリッシュブートキャンプのGENERALこと児玉です。
中学二年生くらいから英語は大嫌いで大の苦手でした。
単語を覚えようとすると眠くなる。文法は例外が多くて腹が立つだけ。長文読解はパラパラ漫画を作る時間。全くもって勉強ははかどらない英語難民でした。
ところが、アメリカに留学したかったんですね。
当時は、とても楽観的で、英語はどうにでもなると思っていました。現地に行けば数週間で喋れるようになると思っていました。であれば、わざわざ日本で勉強する必要も無いだろうと。今考えると身の毛もよだつ程のポジティブ君でしたね。
で、厳密にいうと高校卒業後すぐに渡米したわけではないんです。高校を出てから1年半くらいアルバイトに明け暮れていました。留学資金を貯めるためです。ただ、その間も一切英語には触りませんでした。ちょうど二十歳の誕生日から一週間後に渡米するわけですが、1年半のブランクで、恐らく英語力は「高校で赤点6回」より更に低かったと思います。飛行機の中で、小林克也のアメリ缶というリスニング教材で「blanket please(毛布下さい)」なんて真剣にやっていたくらいです。本当に舐めてました。
渡米したのは1992年で、その頃はskypeもlineもfacetimeも無いどころかemailも普及していない時代です。交信手段は異常に高い国際電話か、1週間かかるエアメールです。アメリカに行くなんて地球の果てに行くくらいの気分でした。祖父が目覚まし時計と、目覚まし時計用の電池を4年分くれたくらいです(電池は日本にしかないと思っていたようです)。ハリウッド映画でも、よく人が死んでいたので、「僕も50%くらいの確率で死ぬ」と真剣に思っていました。家族とは今生の別れかもしれないと覚悟していましたし。そういう意味では、大冒険の始まりでしたし、何としても生き延びてやると覚悟を決めていました。
記念すべきアメリカの最初のご飯がマクドナルドだったんです。
カウンターにいた店員さんは、学生くらいのアルバイト。金髪の女性でした。
そこはバージニア州の田舎の方のマクドナルドでしたので、その女性は、恐らく僕みたいな英語がへたくそな外国人と対峙したのは初めてだったのでしょう。
つまるところ、僕の英語を一言も理解してくれませんでした。
途方にくれたのは、なんと、
目次
“Hamburger, please”(ハンバーガーを下さい)
さえも通じなかったのです。
信じられませんでした。
おいおい、日本の英語教育どうなっとんだ!と赤点だったことは忘れて日本の英語教育が使えない的な一般論にすりかえようとしましたが、それで飯が食えるわけではありません。
仕方なく、何回か続けたのですが・・・・
何度やっても通じません。
金髪高校生の店員も、少し戸惑っていました。
まるで、上司の親父ギャグに遭遇したOLのように、ぎこちないスマイルを浮かべていました。
そこで僕が思いついたのは、「そうだ、発音だ!」という事でした。
つまり、ハンバーガーには、日本人の弱いといわれている「R」が入っているわけで、これをいい感じに巻き舌にしていなかったからだ!と気がついたのでした。
それさえ分かればこちらのもの、
― フッ、金髪のお姉さん、お待たせしたね、とばかりに渾身の巻き舌「R」でハンバーガーを攻めたのでした。
いけーーっ!!!!
「HambuRgeRRR!!!!!!」
巻き巻きの巻き舌でノリノリで発しました!
おるるるるるあああああああ!
という感じでした。
結果は、なんと!
!!
全く通じませんでした。
何度やってもダメ。どれだけ巻いてもダメ。
「HambuRRgeRRR!!!!!!」
「HambuRRRgeRRRRRR!!!!!!」
「HambuRRRRRRgeRRRRRRR!!!!!!」
金髪高校生の店員は更に戸惑っていました。
まるで、親父ギャグの上司を少し好きになっちゃった自分に驚いたOLのように固まっていました。
壁。
高すぎる。
英語の壁。
なんじゃこりゃ!!!!!
でも、ここで諦めたら明日はない。いや、今日すらない。ってゆうかホント死んじゃうかも。
日本にもあった「最も日本に親しいアメリカの味」のマックでさえも、ハンバーガーすら注文出来ない私。終わっている。終わりすぎている。
ただ、人間の生命力とは、凄いものがあるのでした。
人間、追い詰められると閃くものでした。
「そうだ!」
僕は根本的な解決策を閃いたのでした。
― フッ、マクドナルドさんよ。忘れていたが、俺は、ハンバーガーよりフライドポテトの方が好きなんだ。あの塩かけすぎで冷めてシナシナになってもウマいポテトが好きなんですよ。
金髪のお姉さんに心の中で言いました。
― お姉さん、待たせたね。お待たせしますた。私は決して怪しいもんじゃあございません。ただ間違えただけなんです。欲しいものを。本当はハンバーガーじゃなくて、フライドポテト派なんです、ボク。
そして深呼吸してから、渾身の、ハンバーガー改めポテトのオーダーを入れました。
「フライド・ポテイト・プリーズ」
一応、ここは、こしゃくに芋をポテイトとアメリカ人っぽく言ってみました。
金髪お姉さんは、ハッとしていました。
― おお、通じたか!?
と思ったのですが、
そのまま固まる金髪お姉さん。
もしや・・・・
通じていない?
もう一度いってみました「フライド・ポテイト、プリーズ」。
何度も言ってみました。
「フライド・ポテイト、プリーズ!」
「フライド・ポテーイト、プリーズ!!」
「フラーイド・ポテイト、プリーズ!!!」
「フライード・ポティート、プリーズ!!!!」
「フーライード・ポーティート、プリーズ!!!!!」
既に金髪お姉さんは動かない物体と化していました。
まるで、結局、親父ギャグ上司と不倫してしまった自分が信じられなくなったOLのように固まっていました。
後に分かったのですが、
アメリカではフライド・ポテトのことは、「フレンチフライ」と呼ぶのでした。
金髪お姉さんからすると「フライドポテトって何よ、誰か助けて!」といったところだったのでしょうか。
知るか、そんなもん!!!
僕も流石に折れそうでした。
アメリカやばい。
というか、英語がやばい。
つまり、本質的には自分やばくない?
「そうだ、やばいのは君自身だよ」そんな声が頭のなかでこだましていました。
折れそうでした。
ただ、僕には、これで諦めるわけにはいかない理由がありました。
その理由のひとつは、こんな僕を支えてくれた人たちです。
家族、親戚、友人、そして、空手をやっていたのですが、その道場の皆さんでした。支えてくれた皆さんからは、貰ったものがあまりにも大きい。あれほど色々なものを沢山の人から貰ってきた俺が折れていいわけがない。
例えば、空手の師匠が貰った、あの言葉。
「強いやつが勝つんじゃなくて、勝ったやつが強いんだ」
あまりにも強敵と対決するまえに、何度この言葉に励まされたことか。
強敵に見えるかもしれないが、相手を恐れるな。
どんなに不利な状況でもチャンスは必ずある。
勝てる。
勝てるんだ。
その言葉を思い出したとき、日本で支えてくれた人たちが、自分の後ろにずらっと並んで声援を送ってくれているような錯覚をしました。
「がんばれ、ここで負けるな!」と。
僕はここで負けるわけにはいかない。
挫けている場合じゃない。
僕にカチッとスイッチが入りました。
― 金髪お姉さん、悪いが、俺はあきらめないぜ。
金髪お姉さんも、なんだか、すっと背筋を伸ばしてくれたようでした。
丁度そのとき、隣のレジに並んでいた背の高いお客さんがオーダーしたものを紙袋に入れて受け取ったところでした。中身は見えませんでしたが、大きめの袋です。ごそごそとやりながら袋を受け取っていました。
はっ
― そ、そうだ!!!!これだ!!!!!
千載一遇のチャンスがやってきたのでした。
僕は、すっと短く息を吸うと、金髪お姉さんをギラッと見つめました。
金髪お姉さんはハッとしていました。
まるで、親父ギャグ上司と一線を越えたことが、同僚に感ずかれたOLのようでした。
僕は高々と手を上げると、人差し指をすっと伸ばし、ゆっくりと隣のレジの背の高いひとが掴んだ紙袋を指しました。
そして、咆えました。
「same(同じの)!!!!!!」
その瞬間、金髪お姉さんが満面の笑みを浮かべました。そして英語でなんか言っていました(恐らく、あー、あなたあれが欲しかったのね、早くいってよ~みたいなものでしょう)。
まるで、親父ギャグ上司と別れた次の日に合コンでイケメンを捕まえたOLのような晴れやかな笑顔をしていました。
そして注文を確定させると奥から品を持ってきました。
ウキウキでした。
僕もウキウキでした。
このまま僕たち恋に落ちちゃう?くらいのウキウキ度でした。
どうぞ、とばかりにコケティシュに微笑む金髪お姉さんは僕に品物を差し出しました。
サラダ。
でした。
泥の中に引きづりこまれそうな自分が居ました。
自分を鼓舞しました。
「強いやつが勝つんじゃなくて、勝ったやつが強いんだ」
「強いやつが勝つんじゃなくて、勝ったやつが強いんだ」
「強いやつが勝つんじゃなくて、勝ったやつが強いんだ」
僕は、負けない。
負けてはいけない。
今の僕の出来ることをしよう。
今の僕でも出来ること。
それは、、、、
僕はまた腕を高々とあげると、今度はピースのサインを作って言いました。
「two」
サラダを二つもらえました。
これでなんとか飢えはしのげる。
これから始まるアメリカの生活に多大なる不安を抱えながら、僕はサラダをはみました。
つづく