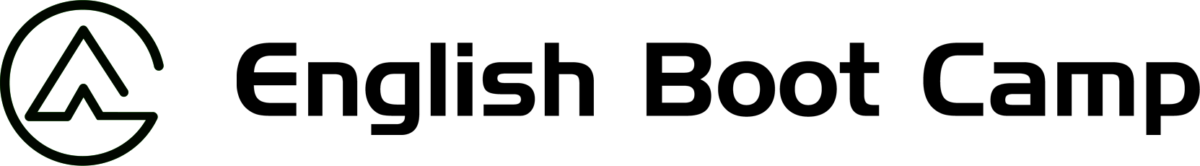【これまでのあらすじ】
ひょんなことから竜宮城に来てしまった僕。竜宮城は、浦島太郎にでてくる大宴会場的な場所ではなかった。ここでは来訪者にそれぞれミッション(任務)が与えられる。それがクリアできればその後の人生で大成功し、できなければ数十年の強制労働をさせられるという異常な場所だ。しかもここはグローバル社会で公用語は英語だという。TOEIC350の僕には乙姫と名乗るドSの英語教官があてがわれた。未だに何がなんだか全く判らなかった。
「これって・・・・」
僕はまじまじと乙姫から手渡されたものを見た。
乙姫から手渡されたものは、スーパーとかでお寿司を買ったときについてくるワサビの小袋だった。それが3袋あった。
「これって・・・・ワサビ・・・ですよね」
なんとも力が抜けた。
人生がかかっているはずのミッションのスタートが、おまけのワサビとは・・・
乙姫によると、竜宮城で与えられた僕のミッションは、「わらしべ長者」みたいなものらしい。つまり何かのアイテムを授かり、それを物々交換していき最後は何か凄いものを手に入れるのがゴール。それを48時間以内にやらなければならないというミッションだった。
その最初のアイテムとして渡されたのがこのワサビ小袋3つだったのだ。
「そうよ、ワサビよ」乙姫は妖艶な笑みを浮かべながらそう言った。
一体、これをどうしろというのだ。
「なんでまた・・・・・ワサビが3袋なんですか?」
乙姫は僕のほうにすっと人差し指を突き出して言った。
「その話の前にね、アンタに話しておきたいことがある」
「・・・なんですか?」
「英会話にとって一番大切なこと」
「・・・一番、大切・・・なこと」
「そうよ。一番大切なこと。英会話にとって一番大切なこと。コミュニケーションの原理を教えてあげる」
「コミュニケーションの原理・・・ですか」
「耳の穴かっぽじってよく聞きなさい」
「・・・はい」
目次
「人は誰しも、とても忙しい」
「・・・人は・・・誰しも・・・とても忙しい」
「そう」
「どういうことですか?」
「いい。人はみんなとても忙しい。アンタ、地上にいたとき忙しかったでしょ」
「ま・・・まぁ、一応サラリーマンでしたから」
確かに日々何かに追われていた。何がそれほど忙しかったのかと言われれば、うまく言えないけれど、なぜか毎日「忙しい」「忙しい」と思っていた。
「サラリーマンだけじゃないわ。誰だって忙しいの。たとえば小学生の男子だって超多忙よ。学校だけじゃなくて塾にも行かされる。テレビも見たければ漫画も読みたい。友達とゲームもしたいしオヤツも食べたい。クラスのあの娘も気になる。もう色んなことに忙しすぎるのよ。常にやらなきゃならないこと、やりたいこと、様々な興味で頭のなかがいっぱいなのが人間なのよ」
「・・・確かに・・・そうですね」
「ってことは、コミュニケーションというものの正体は、そんな忙しい人の時間を奪いにいくものということよ」
「時間を・・・奪う・・・?」
「そう。常に忙しいと感じている人達から、大切な時間を奪って自分の話に気を向けさせる、それがコミュニケーションなの」
「・・・なるほど」
確かにそう言えるのかもしれない。
相手とコミュニケーションをするというのは相手の大切な時間を貰い受けるようなものだ。
「だから、アンタの話が退屈だったり、つまんなかったりしたら、人は直ぐにアンタとの会話から興味を失う。アンタの話を聞いているようで、実は頭の中では直ぐに他のことを考え始めてしまう」
「・・・たしかに」
自分にも身に覚えがあった。相手の話が長かったりつまらなかったりすると、聞いているふりをしながら自然と他のことを考えることはよくある。
「だから、英会話において一番大切なことは・・・」
「・・・はい」
「一番大切なことは、相手を自分に惹き付けることよ」
「相手を自分に惹きつける」
「そう。惹き付けるの」
「あ・・・・それは難しそうですね。惹き付けるような話術も無いですし。そもそも英語が苦手ですし」
ビシッ!「いてっ!」乙姫の激烈デコピンがまたまた炸裂した。
「な・・・なにするんですか!?」
「おだまり!惹き付けるのに、英語が苦手とかは関係ない。英語力は全く関係ないの」
「え・・・英語力が・・・関係ない?」
「先ずはこれを見なさい」
乙姫は例の携帯端末を出すと動画を再生した。
そこには僕が映っていた。
どこからか隠し撮りされたものだろうか。僕が画面真正面に居た。
先ほど乙姫から「How are you?」のテストをされたときに撮影されたもののようだった。
乙姫の姿は映っていなかったが、案の定、乙姫の声で「How are you?」と聞こえてきた。やはり先ほどのテストの場面のようだ。画面の中の僕は、少し考えてから「I’m fine」と言った。乙姫が動画の再生を止めた。
「何か気がついた?」
「え?」
ビシッ!「いてっ!」またまた激烈デコピンをお見舞いされた。
「よく見てなさい。自分の話し方について何か気がつかない?」
「話し方・・・」
「ったく。もう一度再生するから、よく見なさい」
乙姫は先ほどの画面を再生した。
また僕が乙姫の「How are you?」に対して「I’m fine」というまでの一連の場面が流れた。
画面の中には、いかにも自信のなさそうな僕が居た。
乙姫は再生を止めると「どう?」と聞いてきた。
「うーん・・・・自信なさげですね・・・」率直に思った感想を口にした。
「そう。全く自信なさそうよね。アンタ自信なかったの?」
「え・・・いや・・・」
確か、この「I’m fine」と言ったときは、「『How are you?』には『I’m fine』だろ。これは間違えるわけないだろ」と自信はあった。
「・・・そこそこ自信はあったんですけど・・・・」
「じゃぁ、何で自信なさげに見えるか、もう一度見てみなさい」
乙姫が、また先ほどの画面を再生した。
更に画面に映る自分に注目してみた。
「あ・・・・」
「何か気がついた」
「・・・はい・・・」目だった。「目が・・・・自信なさげです」
僕の目は終始完全に泳いでいた。
つまり、正面を見据えることは少しも無かった。下を見たり、上を見たり、考え込んだり、ずっと相手から目をそらして話しているのだ。
「目をそらしていますね・・・・」
「そうよ。アンタは英語を話すとき、ほとんど相手を見ないの。目をそらしているのよ」
「確かに・・・」
確かに僕は真正面を向かず、目をそらしながら話している。
それだと、どうにもビビッているようにしか映らない。
自信がないように見えるはずだ。
「目をそらしているから、自信が無さそうに見えるんですね」
「そう。そしてアンタだけじゃない。多くの日本人英語学習者が英語を話すときに目をそらす。これまで教えてきた子のほとんどがそうよ」
「まぁ・・・気持ちはわかります」
そもそも、そんなに相手の目を見て話すことに馴れているわけでもないし、更に英会話になったときに相手の目を見るなんて、やはり少し抵抗がある。
「あのね。目をそらすってことは自信が無いように見えるだけじゃないの。英語圏では目をそらして話すってことは、何かを隠している、或いは嘘をついているとさえ取られることさえある」
「そ・・・そうなんですか」
「そうよ。アンタ自分が話している相手がおどおどしていて自信なさげで何かを隠しているようなヤツだったら・・」
「ヤツだったら?」
「その人の話を聞き続ける?あんた自身がとても忙しいのに」
「いや・・・」
おそらく聞くのを止めるだろう。
乙姫の言うとおり僕だって忙しいのだ。やらなきゃならないことも、考えたいことも、興味のあることもゴマンとある。そんな自信なさげで何を考えているかわからないような人間の話を聞いている暇はないのだ。表面的には聞いているふりをしても、きっと頭のなかでは他のことを考え始めるだろう。
「そんな状態だったら英語がどれだけ上手でも、相手は聞く耳なんかもたないでしょ」
「確かに・・・・そうですね」
「これって『アイコンタクト』っていうの。聞いたことあるでしょ」
「はい・・・あります。『アイコンタクト』」
「アイコンタクトの効用を教えてあげる。それはね、人は相手から眼をじっと見られて話されると、その人を無視できないの」
「どういうことですか?」
「いい?」というと乙姫は僕の目をじっと覗き込むように見つめて「あなた、このアタシとの会話の最中に今夜のおかずのこと考えることができる?あたしにこうやって見つめられて話されている最中に他のことを一瞬たりとも考えることができる?」
「い・・・いえ」できなかった。乙姫からジッと目を見られると会話に集中せざるをえないのだ。
「そうでしょ。人は目を見つめられて話をされると無視できないものなのよ」
「確かに」
「だから、アイコンタクトは相手の興味を惹くためのシンプルかつ最強の武器なのよ」
目からうろこだった。
アイコンタクトをしないと自信なさげで何かを隠しているヤツに見えるが、逆に相手の目を射抜くように見つめるだけで相手の興味を惹ける。
確かにこれは英語を一言も発する前にできることだ。
「わ・・・わかりました。でも、やはりアイコンタクトには抵抗があるのですが・・・」
アイコンタクトの重要さはわかったが、やはりアイコンタクトには抵抗がある。
「そうだろうね。先ずはこれをみて先ずは特訓しなさい。アイコンタクトのレッスンよ。どうしてもアイコンタクトが苦手な人のためにアイコンタクトのごまかし方も教えているわ」
「ごまかし方?」
「そうよ、ごまかし方。いいから見なさい」
乙姫は携帯端末で動画を再生した。
【こちらがその動画になります。宜しければ再生してみてください】
「なるほど~」
その後、僕は乙姫相手のアイコンタクトの練習した。
なかなかうまくできず、数回デコピンされたのは言うまでも無い。
「よし、これくらいでいいでしょ」ようやく乙姫のお墨付きが出た。
何回か練習することで自信がついた。
そして自信がついたらアイコンタクトへの抵抗がかなり和らいだ。
「まぁ、アイコンタクトしないとかは癖みたいなもんだからね。しっかり矯正しないといつまでたっても出来ないのよ」
「確かに・・・」
「よし。じゃぁ、教えてあげる」
「え・・?」
「あんたがワサビ3袋から始めて最後は何を手に入れればいいのか」
「あ・・・お願いします」
そうだ。それを聞かなくては。
僕が与えられたミッションのゴールは一体なんなのだ?
ワサビ3袋を物々交換で最後は何に変えればいいのだ。
「最後にアンタが手に入れるべきものは『命』よ」
「い・・・命?」
「そうよ、命よ」乙姫は言い切った。
「・・・どういうことですか、命って」
「竜宮城の生物だったら何でもいい。何かが自ら自分の命をあんたに差し出すってことよ。それがアンタのゴール」
「僕に・・・命を差し出す?」
「そう。アンタに命を差し出す。アンタが渡すなんらかのアイテムの代わりに相手がアンタに自分の命を差し出せば、それでミッション成功。あんたは晴れて大成功の人生を手に入れるわ」
「命って・・・・そんな、どうやって」
「知らないわよ、そんなの。でも、アンタのミッションはそれよ」
命を差し出す・・・って、自分のひとつしかない命を僕に渡す、つまり、死ぬということではないのか。
「命を差し出すって、相手は死ななきゃならないってことですか?」
「さぁ、どうだろうね。その辺はアタシは知らない。とにかく竜宮城の生き物の何かが、アンタに命を差し出せばいいってことよ」
「そんな・・・そりゃ無理ですよ、いくらなんでも。自分の命を差し出すなんて、そんなの・・・・」
ビシッ!「いってっ!」またまた乙姫の激烈デコピンが僕の額を襲った。
「おだまり!甘えるんじゃないわよ!」
「・・・・あ・・甘えるって・・・」
流れで竜宮城につれてこられて、この望んでもいないミッションを押し付けられた。ミッションに成功すれば人生大成功らしいが、失敗したら数十年の強制労働が待っているという。運命のいたずらか何か知らないが理不尽にもほどがあると思った。
乙姫が口を開いた。
「いい?望むと望まないと、もうミッションはスタートしたの」
「でも・・・」ビシッ!「いってっ!」またまたデコピンが飛んできた。
「おだまり!もう後戻りはできないの。制限時間は47時間を切ったのよ」
「そんなこと言ったって・・・・」ビシッ!「いってっ!」
「おだまり!アンタにチョイスはないの」
「チョイス・・・って」ビシッ!「いってっ!」
乙姫の目は真剣だった。
「聞きなさい。もうアンタにチョイスはない。そして竜宮城の強制労働はハンパない。ミッションに失敗したら人生が終わったようなもんよ。アンタが望もうと望まざると、もうサイは投げられた。後戻りは出来ないの。あと47時間どう過ごすかでアンタの人生が変わる」
「47時間・・・・」
「そうよ。あとたった2日。たった47時間」
この竜宮城というもの自体が僕の理解の範囲を超えていてかなり現実感の無い話だったが、先ほどから喰らっている乙姫のデコピンの痛さは半端ない。だから、これが夢ということもないだろう。そして、これが夢ではなく、そしてこの乙姫と名乗る女性が本当のことを言っているのであれば、確かにあと47時間の過ごし方で僕の一生は大きく変わってきてしまう。
「・・・47時間。それで人生が決まる・・・」
「そういうこと」
― 「人生」と言われても、、、
正直、そんなに大した人生じゃなかった。
人に誇れるようなことをしたわけでもなかった。
人から羨まれるような人生でもなかった。
でも・・・
「・・・それほどイケてる人生でもなかったんですけどね。ちょうどここに来る前に彼女に振られたし・・・仕事も好調かって言われればそうでもないですし・・・」
乙姫が静かに僕を見つめていた。
「・・・・それでも・・・・僕は結構自分の人生好きだったんですよね・・・・人から見たら大したこと無いような人生かもしれないけど・・」
「フンッ」乙姫が鼻を鳴らして言った「だったら47時間死ぬ気で踏ん張りなさい。その『大したことない人生』を守るために」
どうやら僕は戦わなければならないらしい。
人からみたらイケてない人生かもしれないけど、僕にとっては愛おしいこの平凡な人生を守るために。
乙姫が言った。「ようやく目に力が灯ったわね、アンタ」
「・・・はい・・・まだ何がなんだかわかりませんが、取りあえず、頑張ってみます・・・」
「よし、よく言った。じゃぁ、始めるね」
「え?何をですか?」
「何をってミッションに決まってるじゃない」そういうと乙姫は左手にしていたブレスレットのようなものをいじくり、「では、バイバーイ」と言ってブレスレットのボタンのようなものを押した。
カチッと音がした。
その瞬間、突然僕は雑踏のなかに放り込まれた。
さっきまで乙姫と僕がいた空間は、人っ子一人いない場所だった。誰もいない東南アジアかどこかの繁華街といったほうが正確だろうか。ちょうど千と千尋の神隠しでちひろが迷い込んでしまった世界のように街は存在し、人がさっきまで沢山いたような気配はあるのに誰も居ない、そんな世界だった。
それがカチッという音とともに大きく変わったのだった。
場所はそのままなのに、いきなりそこに雑多な人があふれ出たのだ。
溢れかえる人々は、あたかもずっとそこにいたかのように自然に街に溶け込んでいた。先ほどまでの寂しかった街は、いきなり活気にあふれ、人の熱でムンムンしているくらいだった。
一体何がどうなっているのだ。
そのとき、ドンと後ろからぶつかられた。「Hey watch out!」という非難の声があがり、ぶつかった人は僕を通り越していった。
「な・・・なんなんだ」
ビリッとポケットで何かが動いた。
何だ、と取り出すと、それは先ほどから乙姫がレッスン動画を見せる端末だった。
いつの間にかポケットに入れていたようだ。
それが突然ビリッと震えたのだった。
画面を見ると乙姫が居た。
お気楽に手を振っていた。「はーい」
どうやらビデオチャットのようだった。
「はーいって・・・どこに行っちゃったんですか?って言うかここは何処なんですか?」
「まぁ、簡単に言うとパラレルワールドよ。アンタはさっきまでアタシの英語教育用のパラレルワールドにいたわけ。まぁ、どっちも竜宮城よ、竜宮城」
「パラレルワールド・・・」
「同じ竜宮城なんだけど、次元が違うの。まぁ、深いこと気にしないで。じゃぁ、早速始めて。あと47時間切っているからね」
「え、ちょっと待ってください。始めろって、何から始めればいいんですか?」
「だから、それを考えるがアンタのミッションでしょ。じゃあねー」と一方的に言うと画面が切えた。
そして、そのチャット動画が消えた画面には赤いデジタル表記で数字が現れた。
46:38:27
とあった。そして、一番右の一桁がカチッカチッと数字が、27、26、25・・・とひとつずつ減っている。
考えるまでもない。おそらくこれは残り時間だ。
46時間38分20数秒。
それがミッション達成までの時間のようだ。
1秒1秒を刻むデジタル時計が僕に相当なプレッシャーを与えた。
「マ・・・マジかよ」
― やばい。
どんどん時間が過ぎていく。
僕は左手で握り締めていたワサビ3袋を見返した。
「これを一体・・・どうやって」
最後に「命」と引き換えるということは、全く理解不能だ。
いったいどこの誰が何を対価にしてだったら命を差し出すかなんて考えも及ばない。
ただ、ひとつだけわかるのはいくら何でもワサビの袋3つと命を引き換えにする物好きは居ないだろう、ということだった。
だから、少なくとも先ずやらなきゃならないのは、ワサビを少しでも価値のあるものに交換していかなければならない、ということだった。
僕はきょろきょろ見回した。
ここはどうやら繁華街のようだ。人もわんさか居る。
この中でワサビを欲しい人が居るのだろうか。
ワサビに価値を見出してくれる人・・・・
全く思いつかない。
ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・・・・
全く何も出てこない。
大体ワサビなんて、僕は嫌いだ。
寿司屋でもさび抜きを頼むほどワサビは好きでない。
― こんなもん、誰が好きなんだ、そもそも。
ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・ワサビ・・・・
判らん。
ただ、ワサビだけ食べる人はいないだろうから、やはり、何かにつけて食べるのがワサビだ。ということは、何かを食べようとしている人にしか価値はないのではないか。
このあたりは繁華街だが、どうもレストランとかは無さそうだ。
主にお土産屋というか、怪しげな古物商とか、そんなものが軒並みを連ねていた。
― とりあえず、レストラン街というか食べ物屋が沢山あるところに行ってみるか。
全く具体的なプランは思いつかないが、デジタル表記の時計はどんどん進むばかりだ。
いくら行動力がない僕でもこの状況ではお尻に火がついた。
― よし、とにかく食べ物のエリアに行こう
それには場所を知らなくてはならない。
手っ取り早いのは誰かに聞くことだ。
躊躇している時間はないだろう。しかし、誰かに聞くとなっても・・・
周りを見回した。忙しそうに歩いている人が沢山いたが、誰も見た目は日本人ではかった。欧米系の風貌、ラテン系の風貌、アフリカ系の風貌、世界の様々なところの人達がいたが、どうも日本人っぽい人はいない。
時計の針はどんどん進むばかりだった。
46時間18分50数秒。
げ、もうさっきから20分も経っている。
全然進展していないのに。かなりお腹が痛くなる状況だった。
― よし
僕は意を決して歩いている人に声を掛けた。
「エクスキューズ・ミー」
声を掛けたのはよりによって強面のブロンドの男性だった。背も自分より大分高く威圧感がある。
「What?(何だ?)」とギロっとにらまれた。
怖い。
「ア・・・・ア・・・・アイ・ワント・ツー・・・」
と戸惑っているうちに、男性は肩をすくめるとどんどん行ってしまった。
― くっ・・・・
やはり僕の英語力じゃ無理がある。
心が萎えまくったが、どんどん時間が進むデジタル時計が僕の背中をバンバン押した。
結局7人に試したが、全く話を始めることが出来なかった。
声を掛けた人は一様に不機嫌そうだ。
そりゃそうだ。
英語が下手な外国人にいきなり話しかけれていきなりご機嫌になる人も居ないだろう。
8人目を失敗したときに、カチッと音が鳴った。
そうしたら、一気に人ごみと喧騒が消え、そこは静寂な世界に戻った。
目の前に乙姫が立っていた。
「うわっ」
「うわって何よ。お化けじゃないんだから」
「お、、乙姫さん!」地獄に仏とはこのことか、と思った。
ビシッ!ビシッ!「いってー、なにすんすかいきなり・・しかも2発も!」出会いがしらのデコピンは激烈な痛さだった。しかもなぜか2連発。でも、この痛さすら懐かしいく思えるくらい今の自分は乙姫との再会は心強いものだった。
乙姫は履き捨てるように言った。「1発目はあんたのふがいなさに。2発目は『乙姫様』って呼びなさいって言ってんでしょ!」
「あ・・・・すいません・・・」どんだけ女王様なんだ、この人は。
「あ・・乙姫様。聞いてください。やっぱり僕の英語じゃダメでした」
「は?」
「ですからTOEIC350の英語力じゃ無理ですよ、いきなり英会話なんて」
ビシッ!ビシッ!ビシッ!「いってっ!!!!!!、、、な、何するんですか!3発も」もう僕の額はどうにかなりそうだった。
「あのね、英語力は関係ないの」
「英語力が・・・関係ない・・?」
「そうよ。アンタの英語が通じないのは手の位置が悪いからよ」
「え?・・・手の位置・・・?」
「そうよ、手のポジションよ」乙姫のポジションという発音は相変わらずきれいだった。
「手の・・・・・ポジション・・・・?」
第4話「アンタの英語が通じないのは手の位置が悪いからよ」につづく