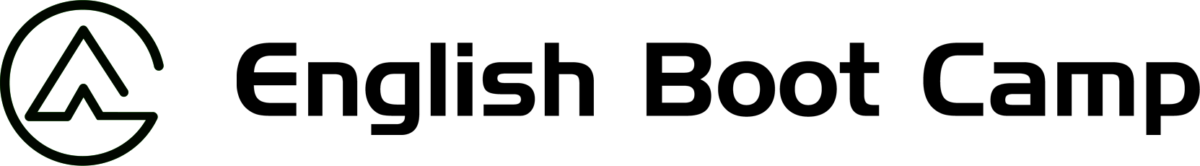【ここまでのあらすじ】
ひょんなことから僕は竜宮城に来たが、竜宮城の公用語は英語だった。英語が苦手な僕(TOEIC350)には「乙姫様」と名乗るドSの英語教官がついた。どうやら僕は48時間以内に「ミッション(任務)」というものを成功させないといけないらしい。乙姫からは、先ずは正しい握手を徹底的に叩き込まれた。いずれにせよ、何がなんだか全くわからなかった。
***
乙姫は、「先ずはアンタの英語でのコミュニケーション力のテストをしてあげる」というと、僕にいきなり「How are you?」と聞いてきた。
―「How are you?」
テストにしては簡単すぎないか。
中学校で一番最初に習うやつじゃないか。
掛け算の九九のように覚えた「How are you?」⇒「I’m fine.」の流れで大正解だろう。ここで流石に躓くこともないだろう。
僕は戸惑いながらも、「I am fine.」と言って、乙姫のその美しすぎる顔を見つめた。
数秒すると、乙姫は
「アンタのHow are you?への返し方は生ゴミ以下ね」
とはき捨て居るようにいった。
そして、例のメガトン級のデコピンを僕の額にお見舞いした。
「いってーーー!!!!何するんですか、もう」 やはり激烈に痛さだ。眼からオデコから星が散った。
「下手な返事のお仕置きよ」
「お仕置きって・・・・『How are you?』って聞かれたら『I am fine.』以外ないんじゃないですか、さすがに?」
「あのねぇ、恐ろしいほど多くの人が鬼の首でも取ったように『I’m fine!』って言って『正しいでしょ?』とばかりにこっちを見返すんだけどね。これが会話的には最悪なの」
「最悪・・・なんですか」
「そうよ。アンタ、『How are you?』ってどんな意味なのかわかっている?」
「え・・・そりゃ、ご機嫌いかがですか、とかじゃないんですか?」
「そうじゃなくて、何でアタシが『How are you?』って聞いたと思ってるのよ?」
「そりゃ・・・こちらのご機嫌を知りたくて」
「違う!」ビシッ!「いってー!!」またデコピンが炸裂した。
「あのね、アンタは王様か!?あんたのご機嫌なんて知りたいわけないでしょ」
「じゃ・・・じゃぁ、お体の具合というか、どんな調子かってことですか?」
「それも違う!」ビシッ!「いってー!!」またまたデコピンが炸裂した。
「あのね、アタシはアンタの主治医か!?アンタの健康状態とかそんなの興味ないわけ」
「え・・・・わかりません・・・・」僕はあきらめて降参した。そもそも間違えるたびにデコピンを喰らうのでは体が持たない。
「ったく。あのね、『How are you?』っていつ使われると思う?」
「それは・・・会ったばかりの時・・・ですか」
「そう。会ったばかりの時よ。話の最初に出てくるのが『How are you?』でしょ」
「はぁ」
「会ったばかりのときに、いきなり本題に入るのではなく、先ずは少し場を暖めたいわけよね、人間って」
「場を暖める・・・」
「そうよ。いきなりビジネス、とか本題に入ってもうまくいくわけないでしょ。先ずはお互い鎧をぬいで関係を温めないと。そのためにアイスブレークが必要なの」
「アイスブレーク?」
「そう、アイスブレーク。会ったばかりの、その場の冷たい空気を暖める、まぁ、つまり氷を割るように、場を暖めるための雑談のことをアイスブレークって言うの」
確かに日本人同士でもいきなり本題に入るというよりは、当たり障りのない話をして場を暖める。いきなり本題ではやはり唐突感がある。
「確かに雑談必要ですね」
「そうでしょ。でもね、アンタとアタシじゃあんまり共通の話題がないわけでしょ?」
「はい・・ないですね」そりゃそうだ。さっき初めてあったばかりだし、お互いのことは毛ほども知らない。
「たとえば、アンタと昨日も会っていて、昨夜アンタが野球の試合でも行くって知っていたら、『How was the ball game last night(昨夜の野球のゲームはどうだった?)』と最初から共通の話題に切り込むはずでしょ。それで楽しい雑談ができそうじゃない。『How are you?』なんてまどろっこしい形で雑談を始めないわけでしょ」
「ま・・・まぁ、そうですね」
「ただ、アタシとアンタではこの場でいきなり話せる特別な話題もない。特に直ぐに話したいトピックが無いの。そんなときに繰り出されるのが『How are you?』なの。『どんな感じですか?』って広い方面に展開できる可能性をひめた自由度の高い一発目が『How are you?』なの」
「なるほど」
「だから、『How are you?』でアンタのご機嫌や、健康状態が知りたい、ってよりは、アイスブレーク、つまり雑談を始めたいだけなのよ、こっちは」
「雑談を始めたい」
「そうよ。それなのに、いきなり『I’m fine!(いいわ!)』とだけ切り捨てるようにパッと言ったら、せっかくこっちが投げた会話のボールをスパンって、『いらないっ!』って地面に叩きつけるようなもんでしょ」
「確かに・・・・」
「『アイスブレークはいいから、さっさと本題、ビジネスの話でもしようぜ』ってなっちゃうかもよ」
「なるほど。流石にそれはヨロシクなさそうですね」
「そうよ。何しろ、人は誰でも自分のことを分かってほしい生き物だからね」
「人は誰しも自分のことを知ってほしい生き物、ですか?」
「そうよ。デル・カーネギーとか人のコミュニケーションを研究している賢人たちが口をそろえて言っているのがこれよ。みんな自分のことを分かってほしい生き物なのよ」
「自分のことを・・・」
「そうでしょ。常に周りから分かってもらい、尊敬されたがっているのが人間なわけ。アメリカの哲学者のデューイは『人間のもっとも根強い衝動は「重要人物たらんとする欲求」』といっているわ。常に、自分のことを凄いと思って欲しい、判ってほしいというのが人間なの。だから・・・」
「だから?」
「だからアイスブレークすっとばしていきなりビジネス、なんてなったら、『この人わたしには興味ないんだ』って超感じの悪いところからスタートになっちゃうわよ」
「確かに・・・」
「そうでしょ。だから『How are you?』って聞かれたから『I’m fine』って返して『どうよ』とばかりに立ち尽くすのは、会話的には最悪なわけ」
「なるほど」
「『正しい言い回し』よりももっと大切なのはコミュニケーションが成り立つかどうかでしょ。英語はそのためのツールにしか過ぎない」
「・・・確かに・・・そうですね」
確かに『How are you? ⇒ I’m fine, thank you!』の流れが英語的にどれだけ正しかろうが、会話として終わっているのであればダメダメだ。でも・・・・
「・・・では・・・どう答えたらいいんですか?」
「ふっ、ほら、今度はこれを見なさい」
乙姫がスマホのようなものを操作すると、また新たな動画が現れた。
【こちらがその動画です。宜しければ再生して下さい】
「判った?」
「ま・・・まぁ」
練習は必要だろうが、言っていることは判った。
「この『How are you?』の返しがイケないと前進できないわよ」
前進・・・そうだ大体前に進むとはどこに進むのだ。乙姫からは僕のは48時間のミッションがあり、それをクリア出来ないと「お陀仏」とか「ジ・エンド」とか言われていた。
「あの・・・・だいたい例の僕の48時間のミッション・・・任務って何なんですか?」
「あ、そうそう。まだ説明してなかったわね」
乙姫は妖艶に微笑み、簡単にいまの状況を説明してくれた。
暴走族から(結果的にだが)亀を助けた僕には、竜宮城にいくチャンスが与えられた。
竜宮城は、浦島太郎のストーリーで描かれているような宴会続きの極楽という場所ではなく、簡単にいうと「人生やり直し道場」みたいなもんらしい。竜宮城に来ると、「ミッション」と呼ばれるものが与えられる。ミッションは人によって違うものだそうだが、この与えられた「ミッション」を成功させると、その後の人生の大成功が保証されるらしい。ただし、ミッションをクリアできないと、そのまま竜宮城で何十年も強制労働をさせられるらしい。つまり、ひらたくいうと竜宮城とは、「いけてない人生」を送ってきた人たちに、亀を助ける善行をした褒美として「人生一発大逆転のチャンス」が与えられる場所とことだった。
「そういえば、浦島太郎って人が昔ここに来ましたか?」
「ああ。太郎ね。やつもここの出身者よ」
「有名なんですか?」
「まぁね。太郎の場合は記憶の消去がうまくいかなかったみたいね、体質的に」
「記憶の消去?」
「そう、ここから帰るとき、ここにいた記憶はすっぱり消去されるの。たまーに、体質的にどうしても残っちゃう人がいるんだけど。で、太郎の場合はそれ。だから竜宮城のことを覚えていたわけ。で、あることないこと周りに言うから、日本では浦島太郎の童話になっちゃったんだよね」
「なるほど・・・ってことは浦島さんにもミッションがあったんですか?」
「そりゃそうよ。みんなあるわ。でも太郎はミッションをクリアできなかったのよ。で、40年くらい強制労働させられたわ。年も取ったし心労で髪も真っ白になっちゃたしね」
「え、じゃぁ、玉手箱で年取っちゃったって話は?」
「ああ、あれは太郎のフカシ。太郎が白髪になったのは単なる強制労働による心労。帰宅したらずいぶん時代が進んでいたのも竜宮城で40年の強制労働を課せられたから」
「ま・・・マジすか。じゃぁ、タイやひらめの舞い踊りってのは?」
「ああ、あれは太郎のミッションが、タイとひらめの養殖場を建設するってのだったから、まぁ、それに失敗したんだけどね。そこから話が膨らんだんじゃない?」
「そりゃ衝撃的な話ですね・・・」
「普通は、記憶が適切に消去されているから、本人たちは覚えていないけどね。・・・・例えば、アンタの知っている日本人だと、ノビーとかヒデとかイエリンとかもここの出身者よ」
「ノビーとかヒデとかイエリン?」
「ったく、自分の国の歴史ぐらい少しは勉強しなさいよ。ノビーとかヒデとかイエリンっていったら信長と秀吉と家康でしょ」
「マ・・・マジですか」
あの天下を統一した歴史の立役者が3人とも竜宮城出身者?
にわかに信じがたがった。
「えっと・・・・因みに信長の竜宮城でのミッションって何だったんですか?」
「ああ、ノビーのミッションね。48時間以内にホトトギスを殺すことよ」
「ま、マジすか」
有名な『鳴かずんば殺してしまえホトトギス』に通じるじゃないか。
「ノビーは優秀だったわ。英語のトレーニングはほぼ要らなかったわね。火縄銃をかっぱらって、それでズドンとホトトギスにお見舞いして、5時間くらいでクリアーしたんじゃないかしら。因みにそのまま火縄銃持って帰っちゃったけどね。それ使ったからあそこまで強かったのよ、織田軍は」
「へぇ・・・そうだったんですか・・・」本当かどうか知らないが、いちいち歴史と辻褄があっているようないないような・・・
「・・・ということは秀吉の竜宮城でのミッションはホトトギスを鳴かすってことですか?」
「そうよ。厳密にいうと『泣かす』ことだけどね」
「『泣かす』っていじめてですか?」
「違うの、感動させて泣かせなきゃならなかったの」
「へぇ・・・しかし、ホトトギスを感動させて泣かすって大変そうですね」
「そうよ。だからヒデは苦労したわ。まぁ、さいわい、彼のミッションの期間は1年以内だったからね。色々試して、それも全部ダメで、最後は冬の寒い日にホトトギスの餌を着物の懐にいれて温めたのよ。それでホトトギスも感動して泣いたってわけ」
「なるほど~」なるほど、秀吉はここでも懐でなにかを温めていたのか。
「じゃぁ、家康はホトトギスが鳴くまで待つってミッションですか?」
「あ、残念。それだけ違うの。家康のミッションは『ナンパ』よ」
「え?ナンパ?」
「そう。1年以内に1000人の女性をナンパするっていうミッション。しかもここグローバル社会だからね。ほとんど外国人の女性ばっかりをナンパしなきゃならなかったの」
「すげぇ。やりとげたんですか」
「まぁね。ただ、奴は999人までなんとか出来たんだけど、最後の1人で困ってね。挙句の果てにアタシをナンパしようとしたわけ」
「え、・・・乙姫様をですか?」このドS女子をナンパとはずいぶん無謀な気がする。
「そうよ。全く舐めてるったらありゃしないから、デコピン300発の刑にしてあげたわけ」
「さ、、300発?」
この悶絶デコピンを300発。それを絶えることができる人間がいるとは思えなかった。
「そうよ。それからよ、イエリンが我慢強くなったのは」
「なるほど~」本当かどうかわからないが確かに家康といえば忍耐の人だ。日本の歴史の新たな一面を見た気がした。
「ほかにも・・・・」乙姫は、ほかにもさまざまな著名人の名前をだした。あらゆる国の人がいた。政治家や経済人、現役のスポーツ選手や、ノーベル賞学者、俳優や音楽家、驚くほど有名な人たちばかりだった。
「超有名人ばかりじゃないですか」
「そうよ。竜宮城でミッションクリアできたら、それだけ大成功出来るってことよ。まぁ、逆にいうとミッションクリアできなくて強制労働を数十年させられて人生棒にふった人間も星の数ほどいるけどね。まぁ、いけてない人生送っている人間が一発当てに来るところだからね、ここは」
一発当てたい人が来るところ、と言われても・・・
確かに尚美に浮気をされたのは最悪だったが、自分としてはそれほど「いけてない人生」とも思っていなかった。それを、そんな何十年の労働をかけてでも人生大逆転狙いたいというものではない。
本来であれば、そのリスクも含めて亀が日本語で丁寧に説明するはずなのが、英語圏用のジェームスという亀がノルマ達成したさゆえに無理やり僕を連れてきてしまった ― ということらしかった。
「それにしても酷いですね。きちんと日本語で説明してくれないなんて」
「でも、アンタ『OK』って言った筈よ。『OK』という言葉を発しない限り亀は人間を甲羅に乗せて飛ぶことが出来ないから」
「あ・・・・」僕はそのときのことを思い出した。ネイティブすぎる英語を分かっているふりをして聞いてしまって最後に「OK」と言ってしまったのだ。「・・・・確かに・・・『OK』って言ってしまいました」
「でしょ?」
「え、ま・・・ただ、あれは英語だったから何いってるか判らなかったのでついつい」
「駄目駄目、そういうの効かないから竜宮城は。大体わかんないならわからないって言えばいいのよ」
「そ・・・そんな」
「といっても来ちゃった限りアンタにもうチョイスはない。もうあきらめてやるしかないよ。48時間しかないし、あ、もう1時間過ぎちゃったわよ。あと47時間」
「え・・・もう始まってるんですか!?」
「そりゃそうよ。到着後すぐにスタートだから」
「えー、マジですか・・・大体まだなにやるか聞いてませんよ」
「ああ。アンタのミッションね。アンタのミッションは簡単に言っちゃうとわらしべ長者みたいなもんね」乙姫は言った。
「わらしべ長者・・・って、あの物々交換して最後は金持ちになっちゃうやつですか?」
「そうよ、それ」
日本のおとぎ話で最初に持っていたワラをどんどん交換していくと最後は長者になっちゃうというあれだ。
「ということで、はい」と言うと、乙姫は僕の手の中に何かを押し込んだ。
「な・・・・なんすか、これ?」僕は手渡されたものを見つけた
「アンタにとってのワラよ。つまり、このアイテムがアンタのわらしべストーリーの起点となるの」
「え?よりによってこれですか?」
「そうよ、ふふふ」と笑った乙姫は超別嬪だった。
しかし・・・・
僕は乙姫から渡されたアイテムを見てげんなりとした。
― こんなのからスタートかよ。
(第3話「アンタ、それじゃ英会話の前に嘘つきだと思われるよ」につづく)