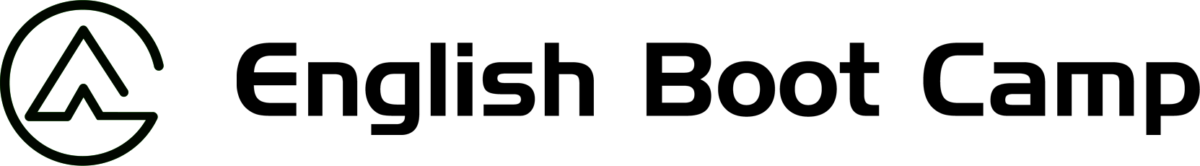エドワード・ホールさんというアメリカの有名な人類学者がいます。
ホールさんは、様々な文化を研究するなかで、日本はとても「高文脈」な社会だと言っています。
この「日本はとても高文脈」というものが、さまざまなコミュニケーションの問題を引き起こします。
「文脈」とは、コミュニケーションの前提のようなもので、「そこは、わざわざ言葉に出さなくても分かるでしょう」と言う部分のことです。
例えば、
Bさん「いいねぇ。でも、せっかくだったら、草津までいかない?」
という会話。
ここには、「温泉」というキーワードは一言も登場していませんが、どこの「温泉」に行こうか、と話していることはお互い文脈からくみ取れます。
こういった言葉に出さないけど、文脈から読み取れるもの。
あるいは、わざわざ口に出して言うまでもないコミュニケーションの「暗黙の了解」。これがホール氏のいう「文脈」というものです。
当然、どの文化においても、人々はこの文脈というコミュニケーションの前提をもって対話をしています。
例えば、先ほどのように、日本で箱根といったら温泉を連想させるように、ドイツで「Wieseに行こう」といったら「オクトーバーフェストに行こう」と連想されるそうです。という形で、どの文化にも必ず文脈はあります。
ただ、その文脈、つまり暗黙の了解が、比較的たくさんある国、あまりない国があるということです。
そして、高文脈、というものは、文脈が比較的多い文化のこと。ホール氏は高文脈の文化として日本、アラブ、地中海の人々等をあげています。
低文脈、というのは「文脈」が比較的少ない文化のことです。ホール氏は、アメリカ、ドイツ、スイス、スカンジナビアの人々等(Page 7)を挙げています。
そこに良し悪し、あるいは優劣はありません。
そして当然ですが、日本が高文脈であることに良し悪しも、問題もありません。
むしろ、個人的には、日本の高文脈は素晴らしいと思っています。
あまり言葉を発しなくても、お互いが察しあいながら意識を通じ合うことができるかたちは、ある意味高度で、美しくもあり、また、温かみすら感じるものだと思っています。わたしたちの誇らしい文化のひとつといっていいのではないでしょうか。
一方で、そんな高文脈に慣れ親しんできたわたしたちに、ひとつ問題が発生するとすれば、それは、「異なる文脈を持った人たちと対話」をするときです。
それはそうです。
馴れ親しんできた、或いは頼り切っていた高文脈の濃い暗黙の了解が、まったく通じない方々との対話なのですから。
同じ文脈内での対話、と、文脈を超えた「異なる文脈をもったひとたちとの対話」は、まったく別のカタチになるでしょう。
英語、という言葉として発せられる部分だけ勉強しても、その対である「文脈」についての有効な知識が無い状態は危険です。
文意がすべてきちんと伝わらないと、(1)情報伝達でのミスが起きる可能性、(2)国際社会において常識や配慮に欠けている人だと勘違いされる可能性、(3)コミュニケーション能力そのものだけでなく、思考力に疑問を持たれたりする可能性があります。
そのようなことが起きないように11個の留意点は以下になります。
- 察することを期待せず、説明することに重点を置く
- 物事を曖昧に残さず明瞭にする
- 間接的な表現をさけ、直接的な表現を多用する
- 文意の途中を飛ばさず、事細かく丁寧に伝える
- 質問を多用する
- 自分と違った意見を尊重する
- 相手の基準で考える
- 男女平等を旨とする
- 少数派に慮った発言をする
- 相手との間に境界線を作らない
- 公私の分別をつけすぎない