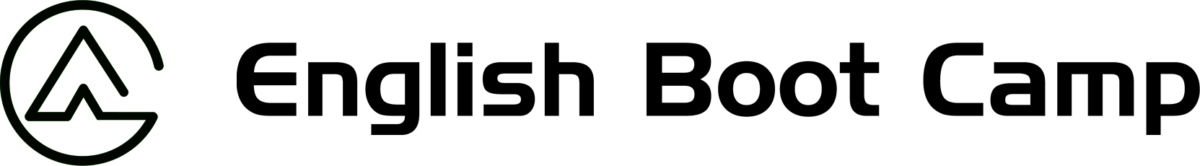眼を覚ますと、なぜか僕は石畳の上に横たわっていた。
― なぜ石畳のうえに居るのだ。さっき派手に入水したはずなのに。
今の状況が飲み込めないでいた。
目の前にヒールを履いた素足があった。
顔を上げると僕を見下すように女性が立っていた。
目が合うと女性は「立ちなさい」と言った。
まったく今の状況が理解できなかったが、その女性が発した声には従わざるをえない何かがあった。僕は、言われたとおりに立ち上がった。
驚くほど体が軽かった。乱闘の末ボロボロだったはずの体はいつの間にか傷が癒えていた。そして、さっき派手に海に入ったはずなのに不思議と服も濡れていないことに気がついた。
女性の顔をまともにみた。ハッとした。
これまで見たどんなアイドルや女優を超越すると思えるほど美しい女性だった。この世のものかと疑うほどだった。その女性を幻想的にしているのは、女性の背後でゆらゆらと揺れる天女の羽衣の帯のようなやつだった。
女性は値踏みするように僕を上から下まで見た。
そして、突然すっと右手を差し出した。
僕の眼の前に右手を差し出したのだ。
数秒戸惑ったが、きっとこれは握手を求められているものだと気づいた。
「あ、、ああ、どうも」僕はそそくさと右手を差し出した。
女性と握手なんて照れるが、また握手なんてなれていないから、とりあえず右手をやんわりと差し出して彼女に握ってもらった。女性とは思えないようなギュッと強い力で握られた。
その瞬間、美しかった女性の顔が般若のようにゆがんだ。
「それじゃダメ!」と彼女はピシッと言い、同時に強烈なデコピンを僕のオデコにかました。
「ギャー!!!!!!」叫ばざるを得ない超ド級の衝撃だった。眼からおでこから派手に火花が飛んだ。
「いっっっってー!!!!!!!!」僕は地面に転がり込み、両手で額を押さえて悶絶した。
女性は女王様のように僕を見下ろしていた。
そして、吐き捨てるように言った。
「あんたの握手は生ごみ以下ね」
初対面の美女になぜ握手をDISられる?
そして、気絶寸前の悶絶デコピンをくらう?
やはり、今日は呪うべき金曜日だった。
この世の不幸をすべて詰め込んだような最悪の金曜日だったのだ。
朝から最悪の金曜日だったのだ。
「な・・・なんなんですか・・・いきなり・・だいたい貴女は何者なんですか?」僕はおでこを抑えながら女性に問いかけた。
「アタシ?」女性はフッと不敵な笑みを浮かべると勝ち誇ったように言い切った。
「アタシは、乙姫様に決まっているじゃない」
― お・・・乙姫様・・・ということは、ここはもしかして・・・
****
その金曜日は朝から最悪だった。
寝坊して遅刻してしまい朝から上司にねちねちと説教され、昼のカレーうどんはワイシャツに飛び散り、単純ミスを連発し女性社員たちからも白い眼で見られ、退社際には部の納涼祭の幹事を押し付けられた。そういえば昼休みに先月受けたTOEICの速報結果をネットでチェックしたらまさかの前回より低い点数350(前回は360)を突きつけられた。
本当に散々なことばかりの一日だったが、退社後にメガトン級の最悪の事態が起こった。
なんとその夜、僕は彼女の浮気現場を発見してしまったのだ。いや、完全に浮気と決まったわけではないが、ほぼ間違いなくあれは浮気だろうと踏んでいる。
交際してもう3年になる僕の彼女、尚美(なおみ)は銀行に勤めているのだが、その銀行の先輩の男と夜の街を2人で歩いているのを偶然見かけてしまったのだ。
以前、尚美と2人でいたときに、その男と偶然に出くわしたことがあった。
小洒落たネクタイとスーツが「いかにも」という感じの、大手町あたりに履いて捨てそうなほどいる自意識過剰の金融マンを連想させた。
NBAだかMBAだかなんだか知らないが、小難しい修士をとるために、今度シカゴに留学する銀行のホープだとかなんとか尚美が嬉しそうに言っていた。ドブにでも転げ落ちないかな、と願わずにはいられないタイプの同性だった。
よりによってその男と尚美が仲良く歩いていたのだ。
金曜日の夜に、繁華街を2人で、だ。
偶然にも遠方から歩いてくる2人を見つけた僕は反射的に電柱の影に隠れた。
そして様子をうかがいながら尚美にラインした。
「今日、突然仕事早く終わった。会わない?」
尚美は「ん?」とスマホを取り出すと、歩きながら器用にメッセージを打ち込み始めた。そして何もなかったように先輩と楽しそうに話しながら歩き続け、僕の隠れている電柱の前を通り過ぎていった。
ブルっと震えたスマホに彼女からのメッセージが届いていた。
「ごねん、いまママと一緒。これから食事~。残念~」
尚美のアホォォォォォォォォォ!!!!!!
僕の心の中の遠吠えはむなしく響いた。
荒れた。
大学時代の友人を呼び出して飲んだ。
友人に絡んだ。
お店の人にも絡んだ。
ちなみに僕のあだ名は「大トラ」だ。
気は小さいし普段はおとなしいが、お酒が入ると豹変する。一言で言うと酒癖が悪い。ビールを3杯くらい飲んだところから気が大きくなり騒がしくなる。「大トラ」になるわけだ。その日も僕が6杯目のビールを頼んだところで友人は「勘弁してくれ」と帰っていった。
飲み足りない僕は、コンビニで酒を買い込み夜の電車に乗り込み海に向かった。酒で気が大きくなっていた僕はワイルドにも夜通し海辺で独りで飲み明かすことにしたのだ。
ところが、海に到着すると、静かなはずの海辺には若者がたむろしてガヤガヤしていた。
暗がりで見えにくかったが、どうやら地元の暴走族かなんかが大きな亀をいじめているようだった。なんと亀にプロレス技をかけているようだった。
とはいえ相手は暴走族だ。普段の僕だったら見て見ぬふりをするのだが、この夜の僕は違った。そう。すでに「大トラ」になっていたのだ。さらに尚美に振られたという心に深い傷を負った「手負いの大トラ」だ。アルコールで薄れた恐怖心と彼女に振られて膨らむ自暴自棄の心。もう暴走族なんか怖くもなんともなかった。
「ヒック、お前ら、亀ちゃんをいじめるな!うぉぉぉぉぉぉ!!!!!」
僕は気勢を発しながら突進していった。
ボコボコにされた。
ひ弱なリーマンが現役の暴走族に勝てるわけがない。僕は10秒で組み敷かれ、そこから散々おもちゃにされた。亀にはかけにくかったであろうさそり固めをはじめとしたプロレス技もたくさん掛けられた。
ラッキーだったのは、数分もたたないうちに、どこからかサイレンの音が聞こえてきて暴走族たちはくもの子を散らすように逃げていったのだ。
海辺には、ぼろ雑巾のようになった僕と、それから亀だけが残った。
冷たい砂がほてった体に気持ちよかった。
亀が僕を見つめていた。
「亀が無事でなにより」と思った瞬間、一気に酔いが吹っ飛ぶことが起こった。
なんと、その亀が突然喋りだした。しかも、驚くことになんとそれは英語だったのだ。
「なんで亀が英語でしゃべっとるんじゃ!!??」
英語を話す亀はビジュアル的にも破壊力があった。
ディズニーに喋る亀のアトラクションがあったが、なんというか、あれは架空の世界とわかりきっているから「可愛い」と受け入れられる。眼の前の亀はリアルすぎる亀である。それが言葉を、いや、それも英語を喋りだす様は相当な衝撃だった。その英語のネイティブっぷりも半端ない。Rの発音時の舌の巻きっぷりも本物だった。
脳が眼の前の出来事をどう処理していいのか戸惑っていた。が、何しろ何をいっているか不明だった。TOEIC350の僕のリスニング力では亀の本格的な高速英語を聞き取ることは無理だった。すべてにおいて圧倒された僕は「?」を顔に貼り付けて、勢いよく喋る亀を見つめていた。
それでも亀は強引に喋り続けていた。
しかし、前から疑問だったが、こちらの顔が引きつっていても「当然伝わっている」と思い込んで喋りつづけるネイティブスピーカーの精神構造はどうなっているのだ。
大体、よく考えたらここは日本なんだから「おいおい、チミチミ、なに英語喋ってんの。ここは日本よ。少しは日本語喋ったらいかが?」と誰も言い出さないのは何故だ。
きっとこれが英語じゃなくてドイツ語や中国語やスワヒリ語で話しかけられたら「ごめーん、日本語で御願い」とサラッといえるのに。英語になると遠慮してしまうのは何故だ。
いや、大体、英語で話しかけられると一気に緊張してしまうのは何故だ。
更に、相手の英語が聞き取れていないことを罪のように感じ、こちらが負い目すら感じるのは何故だ。
そして、英語で話しかけられると、やっぱり理解しているふりをしてしまうのは何故だ。
当然僕もごたぶんに漏れず、亀の英語を理解しているふりをしていた。
亀は5分くらい喋り続けただろうか。
最後に「OK?」と聞いてきた。そこだけ聞き取れた。
困った。今さらもう一度説明してくれとは言えない。
亀は「OK?」と念を押してきた。
これまで分かっているふりをして話を聞き進めてしまったことが罪悪感のようにのしかかり、NOとは言いづらい。
亀はダメ押しの3度目の「OK?」を繰り出した。
仕方なく僕は「・・・・・OK」と言ってしまった。
亀が満面の笑みを浮かべた。
そして、前のヒレを器用に腕のように使い、ボディーラングエッジで乗れ乗れとやった。甲羅に乗れといっているようだった。盗んだバイクで走り出すノリノリの10代のようであった。
僕は仕方なく亀をまたいだ。
すると、亀の甲羅が光りだした。蛍光色の光を放ち始めたのだ。
そしてギューンという音が鳴りはじめ、亀は地上1メートルくらいに浮き上がった。
「ま、、まじか」
脳みそがパンクしそうだった。亀が喋って、それも英語で、更に亀が光って空を飛んで・・
「な・・・なんなんだ!!!」
亀は少し高度をあげ海の上を飛びはじめた。小さな円盤に乗っているようであった。次第にスピードが出た。どんどん海の上空を沖へ沖へと進んで行った。
「こら、ちょっと止めて・・・止めてくれ!!―――――!!」
最後は尋常ではないスピードになった。最終的には日本最速のジェットコースター、富士急ハイランドのドドンパ(@最高時速172km)の20倍くらいのスピードで海の上空を進んでいった。
「ギャーーーーー!!!!!」
僕が気を失う寸前、亀は海に見えた大きな渦に突っ込んで行った。
派手に入水した瞬間、僕の意識はぷつん切れた。
****
そして、眼を覚ましたら石畳の上にいた、というわけだ。
乙姫と名乗る女性に強烈なデコピンをくらい、「あんたの握手は生ごみ以下ね」と何故か握手のやり方をDISられたのだ。
乙姫という女性はオデコを痛がる僕に容赦なく話を続けた。
「アンタの握手は典型的なダメな握手。Dead Fish、死んだ魚と呼ばれている最悪の握手よ」Dead Fishというところの発音が美しかった。
「は・・・?・・・・Dead ・・・Fish・・・?」
「そう。Dead Fish。死んだ魚よ。握ったときに相手から『うわ、なんか生暖かいもの掴まされたわ!』って思われる典型的な悪い握手よ」
― なんなのだ、なぜ乙姫という女性はいきなり握手のことを熱く語りだしているのだ。
「あのね。弱い握手で自己紹介すると、凄く損するわよ」
「・・・損?」
「こんな話があるわ。アメリカの話だけど。2時間近く採用面接をしていた社長が、面接が終わってから社員に『今の人はどうでしたか?』と聞かれて最初に言った一言が『今の人、握手が弱かったな』って話。2時間も面接したのにね。残っていたのは最悪の握手の印象だったってこと」
― アメリカ?・・・面接?・・・は?・・・なんなんだ一体
「そう。弱い握手はよくない印象を相手に与える。自分に自信がない人と思われるかもしれない。握手もがっちりできないなんてコミュニケーションが苦手なのかなって思われるかもしれない。もしかしたら、弱い握手を誰にも指摘してもらえないなんて、残念な人なのかなって思われてしまうかもしれない。そんなマイナスのイメージからスタートしたら損でしょ」
「は・・・はぁ」
― 言いたいことは分かる気がするが、なぜだ。なぜこの乙姫という女性はこんなに握手のことを熱く語るんだ。
乙姫という女性は、すかさずポケットからスマホのようなものを取り出し、僕に渡した。
スマホのようなものには動画再生画面のようだった。
「早速これみて勉強しなさい」と言った。僕がおたついていると「早く!」とイラついた声で言った。どうやら相当の短気らしい。またデコピンを食らってはかなわないので急いでスタートボタンを押した。映像が流れ始めた。
「見た?」
「見ました・・・・けど、何ですかこれは?」
「握手のやり方でしょ」
「いや、それは分かりましたけど・・・」
何なんだ一体。なぜ僕が握手の練習をしなくてはならない。だいたいなぜ乙姫という女性は僕に握手を教える?一体この動画の中の人たちは何者なのだ?わからないことだらけだ。
「・・・・誰なんですかこの動画のなかの人たち。最後になんか微妙に宣伝みたいのは入ってたし」
「あ、彼らのこと?あたしが直接教えるのは面倒だから、地上の人間にお手本ビデオを作らせたのよ。よく出来ているでしょ?ただで作らせたから最後に少し宣伝入れさせてあげたの。それより動画の内容は理解できたの?」
「まぁ・・・はぁ」
「じゃ、練習」乙姫という女性は僕に右手を差し出した。
何故僕が握手の練習をしなければならないかの疑問をはさむ間もなく、早速乙姫による握手の特訓が始まった。
「まだ弱い!」と7回ほどダメだしをくらった。(そのたび強烈なデコピンを放たれ)
そもそもの握る力が弱いのは駄目だったし、ぎゅぅぅぅぅっとゆっくり握るのも却下だった。脇が開いていると脇が甘いといわれた。
8回目に『ちくしょう、握りつぶしてやれ』という具合で思い切り握ったところで、「まぁ、強さはそんなところね」とOKが出た。
― こんなに強く握らないとダメなのか。
それから、握手をしたあとずっと握っていても「早く離しなさい」と怒られた。結局合計12回くらい練習してようやくOKが出た。
「まぁ、そんなところね」
「は・・・・はぁ」
「アンタ、英語苦手でしょ」
「英会話・・・ですか?はぁ、そりゃ、もう・・・苦手です」苦手だし嫌いでもあった。しかし、またなぜ英会話が突然出てくるのだ
「だったら先ずは握手をしっかりしなさい」
「・・・握手・・・ですか?」
「英語が苦手なアンタが英語でコミュニケーションをするなんて、相撲取りがいきなりフルマラソン走るようなもんでしょ」
「相撲取りが・・・フルマラソン?」
「そうよ。あきらかにハンデを負ったレースよ。だったら、やれる事すべてやるべきじゃない?」
「・・・やれること」
「そうよ。弱いグリップの握手で相手から『うわっDead Fishだ』って思われるより、強いグリップの握手をきちんとして一気に相手の信頼を勝ち取るべきでしょ」
「ま・・・まぁ、確かに」
言いたいことは何となく分かった。ただ、というか、それよりも前に何故に突然『英会話』が必要なのだ?
「いや・・・なんでそもそも英会話が必要なんですか?、、、っていうか、なんで・・・お、乙姫さんが僕に握手とか英会話のことを語るんですか?」
「乙姫さんじゃなくて、乙姫様って呼びなさい!」もう1発デコピンを入れられた。
― 乙姫様って呼べって・・・どんだけSなんだこの乙姫は
乙姫は続けた「ってゆうかアンタ、それ知らないでレッスン受けてたの?・・・ってゆうか亀に説明受けなかったの?」
「亀?・・・ああ、亀ちゃん・・・・なんか言ってましたけど・・・・全部英語だったし」
「・・・英語だったの?」
「え、はい。まぁ。全部英語でした」
「・・・もしかして」というと乙姫は空の彼方のほうを見ながらピュッーと口笛を吹いた。そちらの空から蛍光色に光るものが近づいてきた。
亀だった。きっとさっきの亀ちゃんだ。
「あ・・・・やっぱりジェームス!」乙姫が叫んだ。
「ジェームス?」
「またやりやがったな、ジェームスのやつ」
亀は女性の眼の前まで来ると、申し訳ないような顔をして乙姫と何かを話し始めた。
亀は何かを弁解しているようだった。乙姫はガガガガッーと弾丸ネイティブ英語で亀を罵倒した。両方とも高速ネイティブ英語なので何を言っているかはわからなかったが。
ひとしきり会話が終わると、乙姫は「ったくぅぅぅぅぅ、アタシの仕事増やすんじゃないよ!」と、亀にデコピンを食らわした。亀が悶絶していた。
― わかる、わかるぞ亀ちゃん。乙姫のデコピンの痛さは半端なさすぎだ。ご愁傷様。
「まったくどいつもこいつも・・・」乙姫はカリカリしていた。
「ど、、、どうしたんですか」
「あん?・・・・・ああ・・・この亀、ジェームスっていうんだけどさ、この子英語圏用の亀なんだよね。でもノルマがきつくなるとたまに日本人つれてきちゃうのよ」
「え?ノルマ?」
「あー、まぁ、簡単にいうと日本人には日本人用の亀がいるの、庄之助と、紅太郎ってのが2匹ね。竜宮城に来るかこないかって人生にとって一大事だから間違えが起きないように亀がしっかり説明する必要があるわけ。だから日本人のために日本語を喋る亀がちゃんといるわけよ」
乙姫は続けた。
「まぁ、来ちゃったものはしょうがない。ひとつ言っておくとここの、つまり、竜宮城の公用語は英語なの」
「え・・・英語・・・というか、ここ、やっぱり『竜宮城』なんですか?」
「そうよ。当たり前じゃない」
確かに亀を助けて連れてこられた場所に天女の羽衣みたいのが背後に揺れる乙姫様と名乗る女性がいたら竜宮城しかないだろう、それはうすうす気がついていた。ただ・・・
「で・・・でも、なんで英語なんですか?ここ?」
「あのね、竜宮城は国際水域にあるのよ、グローバル社会に決まってるじゃない」
「・・国際水域・・・でも乙・・・乙姫様は今僕に日本語を喋っているじゃないですか?」
「ああ、あたしは日本人用の英語教官だからね」
「英語教官?」
「そうよ。英語はあたしがサポートしてあげるから、アンタは48時間以内にミッションをクリアーするのよ。クリアーしないとお陀仏よ」
「ミッション・・・?」
「そう。ミッション。それを48時間でクリアできないとお陀仏。終わりよ、ジ・エンド」
「な、何なんですかその48時間のミッションって」
「まぁ、それはこれから説明してあげるけどね、そのまえに問題はアンタの英語でのコミュニケーション能力。それじゃ即死よ」
「コミュ・・・・え?・・・即死?」
「そう。アンタの英会話じゃ生き残れない」
「え・・・英会話なんて無理ですよ。なんせ僕英語苦手ですもん。TOEIC350だったし。しかもなんだかわかりませんが48時間しかないんでしょ。たった2日じゃないですか。無理ですよ」
「無理じゃない。ってゆうか英語力なんか関係ない。英語力なんかTOEIC350もあれば先ずは十分」
「TOEIC350で・・・」
TOEIC350というのは相当低いと自分でも思う。おそらく高校卒業程度とかそれくらいの英語力ではないか?
「そうよ。TOEIC350。TOEIC350あればたった2日間で喋れるようになれる。なぜだか知りたい?」乙姫は妖艶な表情を浮かべた。
「は・・・はぁ・・・まぁ」
何がなんだか判らないが、何しろ英語でコミュニケーションが取れないとかなり不味いらしいことだけはわかった。
「先ずはアンタの英語でのコミュニケーション力のテストをしてあげる」
「テスト・・・・?」
「そうよ」と乙姫はにっこり笑うと
「How are you?」
といきなり英語で聞いてきた。
― How are you?
これに答えることがテストだというのか?
であれば簡単すぎる。中学校で一番最初に習うやつじゃないか。
例のあれを言えばいいんだろう?
これが本当にテストなのだろうか。
僕は戸惑いながら乙姫のその美しすぎる瞳を見つめていた。
(第2話「アンタの『How are you?』への返し方は生ゴミ以下ね」につづく)